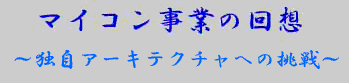2010年6月13日、小惑星探査機「はやぶさ」が地球帰還に成功し、日本中が喜びに湧き上がった。同年8月には東京駅近くのオアゾ内で「おかえり、はやぶさ」の展示会が行われたが、開館前から大勢の人がおとずれ、オアゾビルを取り巻くほどの人気であった。
テレビカメラは、展示品を見終わった一人の初老の男性が涙ぐんでいる姿を捉えていた。
「はやぶさを見ての感想はいかがですか」との問いかけに、
「・・・とても感動しました。途中で数々の障害に遭いながらも、それを乗り越えて7年ぶりに、やっと帰ってきた姿が、自分のこれまでの人生と重なって・・・」。
続く言葉は感涙にむせんで聞き取れなかったのであるが、「はやぶさ」の大人気の背景にはこのような感想を共有する人が多くいたのだと思われる。
それからしばらくして、日立時代の知人から届けられたメールをみて、私ははっと驚いた。「はやぶさ」の制御用コンピュータに「SHマイコン」が使われていたとの知らせである。
SHマイコンは日立半導体グループの総力を結集して開発した独自アーキテクチャのマイコンだ。「はやぶさ」に使われていたCPUはSH-3(SH7708の60MHz版)であり、OSはμITRONであった。システムは3重冗長系として、高い信頼性が確保されていた。
このような大事なミッションになぜSHマイコンが選ばれたのか?
端的にいえば、消費電力が少なく、高性能のマイコンだったからである。即ちMIPS/W(ミップス・パーワット)の値が世界の最高レベルにあったからだ。SHマイコンは開発当初から、新しく開けるモバイル機器の時代(ノマディック時代)を目指して、MIPS/Wを最重要指標として取り組んできたのであった。そのためにアーキテクチャ設計、ソフトウエア、回路技術、プロセス・デバイスなど各分野の技術陣が最先端の知見を持ちよることによって、最高レベルを達成したのである。その成果が省エネを必要とする宇宙用機器の要求にマッチして、「はやぶさ」での採用につながったのである。
「よくやったぞ! SHマイコン!」
SHマイコンに直接・間接に携わった日立半導体OBの多くが快哉を叫んだのではないだろうか?
本書は日立の半導体部門におけるマイコン事業立ち上げの紆余曲折を記したものである。米国からの技術導入に始まり、独立の過程で発生した多くの障害を乗り越えて、最後に到達した独自アーキテクチャがSHマイコンである。それからおよそ20年が経過し、SHマイコンは日本を代表するオリジナル・アーキテクチャのマイコンとして、あらゆる分野で使われ、世界中で活躍している。今日、マイコンはあらゆるハイテク分野における、もっとも重要な構成要素であり、マイコンを措いてハイテク製品はありえない。独自アーキテクチャのマイコンはどのようなチャレンジを経て生み出されたのか・・・これが本書のテーマである。
ここで、日立半導体の各製品世代の変遷を辿って、マイコンの位置づけについて述べておきたい。
第一世代製品はトランジスタである。ラジオ用、テレビ用向けとして1950年代後半から立ち上がり、60年代半ばに黄金期を迎えた。
第二世代製品はIC/LSIである。60年代半ばからコンピュータ用、電卓用向けとして立ち上がった。特に70年代初頭から電卓用カスタムLSIが急増して黄金期に到った。しかし、74年に始まるオイルショックで打撃を受け勢いを失った。
第三世代製品はメモリである。インテル品互換の1KDRAMが製品化されたのは73年であったが、70年代後半に開発された64kDRAMや16kSRAMが世界トップの座を占めて大躍進した。80年代前半に黄金期を迎えたが、メモリ大不況(85年)と日米半導体協定(86年)によって苦戦を強いられることになった。
第四世代製品が本書の主題のマイコンである。日立で最初に製品化されたのはインテル品互換の4ビットマイコンであり、74年であった。続いてモトローラより技術導入した8ビットマイコンが76年に市場導入された。その後、81年のCMOSマイコンの導入、85年のZTATマイコンの導入など、ユニークな製品の開発が進められた。しかし、「独自アーキテクチャ」を持たないが故に、行く手を阻まれることになる。そして、このときの屈辱感が独自アーキテクチャ確立への秘められたエネルギーとなる。
独自アーキテクチャのH8マイコンが88年に市場導入されたが、その直後に裁判沙汰となる。その決着を経て、92年に市場導入されたのが新型RISCアーキテクチャのSHマイコンである。SHマイコンはデジカメ、ゲーム機、カーナビ、電子楽器向けなどの新分野製品の立ち上げに貢献する。96年にはマイクロソフト社のWindows
CEが搭載されて、ハンドヘルドPC市場を制覇し、マイコンの黄金時代となる。98年のエルピーダメモリの設立によってDRAMが分離された後は、マイコンが文字通り日立半導体の大黒柱となり、その形は今日のルネサス
エレクトロニクスに引き継がれている。
日立のマイコン事業推進の過程で、世界の潮流を先導するような技術開発を3件挙げることができる。詳細は本文に譲るとして、以下はその概要である。
第一は高速CMOS技術のマイコンへの適用である。70年代においてはNMOS技術がマイコンの主流であったが、CMOS化は81年に日立が先陣を切ったものである。今日では全てのマイコンがCMOS化されているのみならず、その影響はメモリ、ロジック、アナログなどに波及して、今日の半導体エレクトロニクスの基盤となっている。
第二はZTAT(Zero Turn Around Time)、F-ZTAT技術のマイコンへの適用である。マイコンのROM部をフィールド・プログラマブル化して、ユーザーから見たTATをゼロにするというコンセプトである。現在では、F-ZTAT(フラッシュ・オンチップ)が殆んどのマイコンに使われており、マイコン技術の主流になっている。
第三は新型RISCアーキテクチャを採用したSHマイコンによって、世界最高レベルのMIPS/W(ミップス/ワット)を実現したことである。これによって「デジタル・コンシューマ」と称される一群の新製品市場が立ち上がり、アナログからデジタルへのパラダイムの転換が引き起こされた。さらに、「ノマディック時代」とも表現される新しいライフスタイルを生み出す要因ともなっている。
このような画期的な技術開発を進める過程において「アーキテクチャ」の独立性がいかに重要であるかを痛いほど知らしめられたのであった。詳細は本文に譲るとして、ここではその大まかな流れについて述べることにする。
日立におけるマイコン事業が本格的に立ち上がったのは、モトローラ社(以下、モ社と略す)と技術提携してからである。先方からは6800系マイコンを導入し、日立からは当時世界最高性能の自動ボンダー技術を供与して技術交換が行われた。いわばWin-Winの関係でスタートしたのである。
日立はモ社にとっても有力なセカンドソースであり、両社が結束してインテル陣営を追撃する体制となったのである。スタートから5,6年の間、両社の関係はハネムーンのような状態が続き、この道の先輩としてのモ社から学ぶことも多かった。しかしながら、その関係は次第に難しくなる。市場における競合が激しくなると共に、「アーキテクチャ」を巡る問題が顕在化してきたのだ。ハネムーン状態から次第に競合関係に変化していった。
その経緯はおおむね次の三つのステップに分かれる:
CMOS化路線での対立
日立が先導したCMOSマイコンに対してモ社はネガティブな態度で終始した。「アーキテクチャ」がモ社のものである故に、CMOS化の進展が阻まれたのである。
ZTATマイコンのワインドダウン
日立が開発したZTATマイコンも、「アーキテクチャ」が自社のものでないが故に、モ社によって製品化のライセンスが与えられず、市場導入の後で、撤退を余儀なくされた。
H8マイコンを巡る裁判
H8マイコンは日立の独自アーキテクチャをベースに開発されたのであるが、モ社は「アーキテクチャが似ている」ことを理由に特許侵害を申し立て、裁判沙汰に発展した。
両社の関係はそのステップごとに険悪化の道を辿り、最後は「裁判」という形に持ち込まれたのであるが、これは日立の長い歴史においても過去に例のないことであった。
上記の三つのケースは日立のマイコン陣営にとって耐え難い屈辱であり、そのために秘められたエネルギーが「アーキテクチャ独立」への道を推し進める力になったのである。
このような歴史を背景にして開発されたのがSHマイコンである。その基本的な狙いは、「まったく新しい独自アーキテクチャ」をベースに、来るべきノマディック時代に備えるための、エネルギー効率の高いマイコンの開発である。半導体事業部のみならず、研究所やユーザー事業所も含めて、日立のマイコン技術者全員が、アーキテクチャの独立のために奮起し、世界トップレベルの製品開発を目指して結集したのである。
今日、殆んど全ての電子システムの中枢にはマイコンがあり、マイコンは半導体ビジネスの真髄である。その真髄を守り、生かしていくためには完全にコントロールできるアーキテクチャを持たなければならない。新しいアーキテクチャを世に送り出し、育て、実らせるには10年単位の歳月が必要である。H8マイコンもSHマイコンも今では大きな実を結んでいるが、決して平坦な道を辿って出来上がったものではない。独立したアーキテクチャを確立するまでにいかなるチャレンジがなされたかを記録にとどめ、後世に残すこともそれなりの意義があるものと思う。
2010年5月、アップルが株式時価総額においてマイクロソフトを凌駕し、世界に驚きが走った。これは一つの歴史の転換点を示す象徴として捉えることができよう。そのメッセージは「Wintelの時代、即ちパソコンの時代が終焉し、モバイル機器の時代、即ちノマディック時代が到来した」と要約することができる。
パソコンの時代にはMIPS値そのものが重要であったが、ノマディック時代における重要指標はMIPS/Wである。もちろんMIPS/Wは象徴的な表現であり、一般的には「性能対消費電力比」、あるいは広義のエネルギー効率である。従ってデバイスによって、MOPS/W、FLOPS/Wなどの指標があり得るし、モバイル・メモリなどの場合にはスピード/Wが重要な指標となる。
このような時代の変わり目にあたり、半導体分野のみならず、広くエレクトロニクス分野、あるいはIT産業に携わる方々に対して、次のようなメッセージをおくりたい。
即ち、パソコン主流の時代からモバイル機器を中心とするノマディック時代が開けることは日本にとって大きなチャンス到来である。日本のエレクトロニクスの伝統的な強みは、MIPS/W、即ちエネルギー効率の強みである。ポータブルラジオ、ポータブルテレビ、ウオ―クマン、電卓などなど、世界をリードした製品は全てエネルギー効率において圧倒的な強みを持っていた。今こそ、「そうだ、新しいMIPS/Wの時代が来たのだ!」という視点で世界戦略を構築して欲しい。
私が日立半導体事業部の製品開発部長に任命されたのは1969年である。その2年後の71年にインテル社が世界で始めてのマイコン(4004)を市場導入し、半導体業界、システム業界の双方に大きな衝撃を与えた。カスタムLSIが中心であった時代に、まったく新しいシステム構成法が現れ、パラダイム転換をもたらしたのである。今年は奇しくもマイコンの市場導入から40周年の記念すべき年にあたる。この間、私は日立のマイコン事業に深く関わってきたわけであるが、その過程を一言で表現するならば「独自アーキテクチャ確立のための独立戦争」であったといえる。
現役を離れて、とうに古希を過ぎた今、このような歴史を書き残すことも許されるのではないかと思う。むしろそれは自分に課せられたつとめであるのかも知れない。本書が単なる「思い出話」としての読み物でなく、半導体、エレクトロニクス、IT産業に携わる皆様に対し、「温故知新」の一助として、参考に資することができれば幸いである。
日本半導体の低迷が云われて久しいが、エレクトロニクス分野、IT分野に新しい波が押し寄せている今こそ、これをチャンスと捉えて飛躍するときである。 2011年7月4日