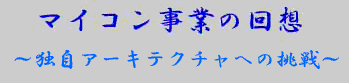1976年12月、日立の半導体事業部において大きな人事・職制の変更が行われた。その前年に事業部長が今村好信氏から重電部門出身のA氏に代わったことはすでに述べたが、職制変更にあたっての同氏の狙いは「事業部中心」になっていた半導体事業部の組織を日立伝統の「工場中心」に戻すことであった。
当時の日立では発電機など重電部門が主流であり、特定の顧客から提示されたスペックにしたがって忠実に製品を作るのが事業の基本である。従って「How to
make?」(スペックどおりの製品を高品質で、安く、早く作るにはどうするか?)が事業の鍵を握っており、「工場」が中心的な役割を持つ慣わしになっていたのである。一方、半導体部門においては、顧客は不特定多数であり、「What
to make?」(どのようなスペックのものを作るか?)がより一層重要である。そのために、69年11月に体制変更が行われ、半導体では例外的に「事業部」中心の体制になっていたのだ。
新事業部長の主張は「オイルショックを契機にして赤字転落したことの一因は半導体部門の体制が、社内で例外的な形になっているからだ」というものであった。この考えをもとに、組織の再編成が行われ、日立の伝統の「工場中心主義」に戻すことになったのである。
私が部長をしていたIC開発部も事業部所属から武蔵工場の中に取り込まれることになる。そしてこの異動に関連して私自身も開発部長を解任されたのであった。LSI事業が赤字転落になったことの責任を取らされたのであるが、高い山から谷底へ転落するような思いであり、入社以来はじめての挫折であった。
この時期、世界の半導体分野においては、大きな潮流の変化が起こりつつあった。電卓の市場はいわゆる「電卓戦争」の激化によって、頻繁なモデルチェンジと価格ダウンに見舞われていた。次から次に新モデルを開発しても、すぐに製品寿命が尽きるという事態となり、カスタムLSIの方式で追随することが難しくなっていた。
これに対し、メモリ・マイコンなどの標準品を中心とした分野が勢いを増していたのである。そして、ここではインテルを中心に新興勢力が圧倒的にリードしており、米国にはもっと学ぶべきものがあることを強く感じていた。
部長解任後の私の新任務は「戦略企画」であり、幸にも事業部長直属である。この辞令が出てから程なく、私は自分の思いを直接事業部長に進言することにした。「戦略企画の業務のためには、国内に止まっていてもなかなか将来展望が開けない。米国シリコン・バレー内に技術情報拠点を設けるべきではないかと考える」と提案したのである。
却下されるかも知れないと覚悟はしていたが、案ずるより生むが易し、事業部長から「具体的に検討してみたらどうか?」との返事をいただいて、将来に一縷の希望の光を見る思いであった。
まず初めに、その年も暮れかかった12月23日に(中研)の企画室に相談に伺った。(中研)ではこの当時カリフルニア州のマンテンビューに「SL」(サンフランシスコ・ラボ)と称するリエゾン・オフィスを構えており、企画室がその管掌に当たっていたのだ。山田弥彦氏をはじめ猪瀬、遠藤の各氏など6名が駐在しており、調査活動と研究活動を進めていた。予算は半期で約70M\とのことであり、経費の内訳などを教えてもらった。
半導体事業部の場合、当面、2人〜4人の体制でスタートするとして、経費もその半分程度で済むことがわかった。
メンバーについては、半導体事業部(以下、子半)とデバイス開発センター(以下、デセ)から当面各1名を選出することにし、場所は(中研)/SLの近くにおいて協力し合うことも幹部間で確認された。そして、その年が明けると、(デセ)から川勝文麿氏が常駐メンバーとして選ばれ、一緒になってリエゾン・オフィス設立の準備を進めることになった。同氏は元々戸塚工場の出身であり、半導体のみならず通信システムにも通じており、幅広い知識を有していたため、このような活動には最適の人選であった。
2月に入って、川勝氏と共にSL所長の山田弥彦氏にお会いして具体的なアドバイスをいただくことができた。例えばオフィス・スペースの広さと価格の関係、秘書の給与、調査会社との契約の仕方など。さらには、通信手段としてのテレックス端末、電話、事務机、什器類の準備など、初めてのことばかりだ。
4月になると米国拠点計画は事業部内で正式に認可され、名称はHICAL(Hitachi Californiaの略称)と決まった。また、(子半)からは立木卓男氏が駐在要員として選ばれ、準備はほぼ完了した。同氏は電卓のシステム技術関連の仕事をしていたが、MOSロジックの分野では幅広い知識があり、また物怖じしない性格もこの仕事に最適であった。5月末には秘書のテリー・ケリーを含めてすべてのメンバーがマンテンビューのHICAL事務所に顔をそろえた。
そして77年6月1日を以ってHICALの設立日とした。私が所長となり、川勝氏、立木氏、秘書のテリーの4名で活動がスタートした。これが後に米国における重要な設計拠点となるHMSI(Hitachi
Micro-systems, Inc.)の前身である。
私は人脈の構築を重点として、スタンフォード大学を初めDataquest社、Gnostic Concept社,Creative Strategy社(いずれも半導体調査会社)などの幹部とのコンタクトを通じて協力を仰ぐことにした。川勝氏は経理全般を担当すると共に、主としてメモリ関係の動向調査に注力し、立木氏が主としてマイコンの技術動向調査を担当する体制とした。
3人が分担して半導体関連の学会、セミナー、講演会などへ出席すると共に、当時新しく勃興しつつあった、半導体技術関連のベンチャー企業にもコンタクトして将来への備えを固めていった。
その中には、オズボーン・アソシエーツ(マイコンのコンサルタント、特に6800系のシンパであった)、ピコデザイン(LSI設計サービスの会社)、モスエイド(メモリの技術コンサルタント、特にDRAMに強かった)などが含まれていた。
また、スタンフォード大学では私の恩師のリンビル教授の計らいで、マイコンの応用研究を委託することになり、先方ではガーランド教授が担当し、当方は立木氏が担当して共同研究がスタートした。余談であるが、そのため立木氏は名門として知られるスタンフォード・ゴルフ・クラブで、いつでもプレイする特権をも与えられた。ゲストを招待することもできたので、私も何回か一緒にプレイしたことがある。プレイ代は当時としても破格の3$であった。
HICALの操業時代で、今でも記憶に残るのは2代目秘書のスーザンだ。仕事もよくできたが、ユーモアもあり、なかなかの傑物であった。若いころミス・パロアルトに選ばれたとのことで、その面影を残していいた。また、ゴルフはプロ並みの実力があり、折に触れてゴルフ談義が弾んで、いろいろなコツを教えてもらったりしたものだ。
ある日「牧本さん、ゴルフで一つだけ大事なことを教えましょう」という。「それはヘッドアップをしないこと。これさえ守れば大丈夫!」。さらに付け加えて「仕事も同じですよね! アハハハ!」。彼女一流のユーモアで、実に愉快なことが多かった。HICALを軌道に乗せた功労者の一人であるといえよう。
写真1は秘書が初代のテリーから2代目のスーザンに交代する頃のものであり、写真2は立木氏とともに、オズボーン・アソシエイツ社を訪問したときのものである。

写真1 HMSIの前身(HICAL)設立の頃(1977年)、マンテンビュー事務所
左から牧本、テリー(初代秘書)、スーザン(2番目秘書)、川勝氏

写真2 オズボーン・アソシエイツ社(マイコン・コンサルタント)
を訪問、 左から立木氏、オズボーン氏、牧本
HICALでは定期・非定期の形で調査結果をまとめて「HICALレポート」を作成し、企画室・マーケティング課(金丸課長)宛てに送付し、(子半)の幹部に配布してもらった。米国における半導体動向を幹部向けにわかりやすくまとめることに腐心したのだが、個別的、表面的な動きよりも、大きな産業構造の転換が起こりつつあることに注意を喚起した。特に、メモリとマイコンに関する情報に重点を絞って、常にその重要性を強調した。
このレポートが幹部を動かしたのか、HICALが発足して間も無く、突然の人事異動が発令される。8月の定例組織変更において、武蔵工場の新組織として「メモリ・マイコン設計グループ」(略称、M設)が設置され、そのグループ長として私が任命されたのである。当面はHICAL所長を兼務する形であった。
部長解任から8ヶ月しか経っておらず、当時の日立の常識では考えられないことであったが、この人事を推進したのは、当時武蔵工場長の柴田昭太郎氏であることを後で知った。半導体の難しさを知る同氏が新事業部長に対して「このポストがつとまるのは牧本しかいない」と強く推薦して、前例のない人事が実現したのだと聞いた。忘れることのできない人の絆であり、それがなければ私の半導体人生はまったく別のものになっていたと思う。メモリ・マイコンというこれからの半導体の主戦場でチャレンジできる機会が与えられたことに気の引き締まるような高揚を覚えたのである。
さて、新設された(M設)はまさにヨチヨチ歩きの状態からのスタートであった。当時の設計部としては第一設計部(MOSデバイス担当、約200名)と第二設計部(バイポーラ・デバイス担当、約100名)が主力である。それに比し、(M設)は20名にも満たない所帯で、第一設計部の10分の1程度の陣容であった。しかし、この少数精鋭の部隊にはメモリ・マイコンという、これからの伸び筋分野を担当するという使命感があり、意気高い設計集団としてがんばった。「坂の上の雲を目指して」という表現がぴったりだったかもしれない。この時点では「設計部」の名前もつけられないほどの小さな所帯であったが、明けて78年2月には陣容も幾分強化され、晴れて「第三設計部」の名前を頂戴することになる。私もほぼ一年ぶりに「部長」の肩書きへの復帰が叶ったのであった。この時点で私は部長業務に専念することになり、HICAL所長は川勝氏にバトンタッチしたのである。
HICALのその後の移り変わりについて簡単に触れておきたい。新しい所長になった川勝氏は現地法人化を進めて78年内にそれを実現、社名をHMSIとして、初代社長に就任した。同氏に続いて、1980年には中野邦夫氏(故人)、1984年には野宮紘靖氏、1987年には安井徳政氏が順次社長に就任することになる。
安井社長のときにHMSI設立10周年記念行事が行われ、私も参加することになった。当時、高崎工場長をしていたが、「HMSI Founder」として安井氏から特別に招待していただいたのであった。
閑話休題。先般、安井氏から「HMSI設立10周年記念」の時に作られたブロシュアをいただいた。そして、図らずもその中に私からHMSIへの祝辞が載っていることを見つけてのだ。そのポイントの部分のみを抜粋すると、
「To see HMSI grow is like seeing my child grow. ---- When HMSI was founded
in 1977, the product structure was changing from custom to standard product.
--- The semiconductor industry is turning around again, from standard to custom
product such as ASIC. ----」
(HMSIの成長を見るはわが子の成長を見るが如し。・・・1977年の設立の頃、製品構造は「カスタム品」から「標準品」への移行期にあった。・・・今はまた、製品構造の転換期にあり、「標準品」からASICのような「カスタム品」に変わりつつある。・・・)
この内容は4年後の1991年、エレクトロニクス・ウイークリーによって「牧本ウエーブ」として紹介されたコンセプトの一端である。その着想を得たのは高崎工場へ転勤となった1987年頃であることは記憶しているが、はっきりした書き物として残っているのは、おそらくこの祝辞だけだと思う。貴重な資料に巡りあえたことをうれしく思っている。安井氏に続いて初鹿野凱一氏は1991年から98年までの長期政権となり、その後任にはピ−ター・クラークが就任してマネジメントの現地化が進められ、後に販売部門と合併するまで社長をつとめた。
この間にHMSIの業容も技術調査業務中心から、設計、開発分野へと広がり、さらには「プロダクト・デフィニッション」でも重要な役割を果たすようになった。即ち、日立半導体の米国設計拠点として事業部全体をリードするような形に成長して行ったのである。特にマイコンの関連ではHMSIに優秀な技術者が終結して、重要プロジェクトの中心となった。
例えば83年にHMSIが開発したCMOS 16ビットマイコン(63000)は世界初のCMOS版として画期的な製品となった。また、CMOS/BiCMOSキャッシュメモリの開発やSHマイコンとDSP機能とを同一チップに集積したSH-DSPの開発でも重要な貢献をした。
しかし、HMSIが果たした最も重要な役割は94年から始まった、マイクロソフト社とのWindows CE(同社のコンシューマ分野向けOS)のSHマイコンへの搭載プロジェクトである。共同開発のきっかけを作ったのはHMSIのトニー・モロヤン氏であり、実際の開発過程においても
HMSIが日立サイドの中心的な拠点となったのである。Windows CEはSHマイコンの基盤を拡大・強化し、その知名度の向上に大きな貢献を成し遂げたのであるが、本件については別途章を改めて述べることにする。
(2011年8月13日)