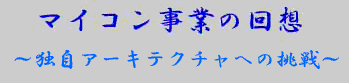「粉砕作戦」に学ぶ
MGO(Micon Grand Operation:マイコン大作戦)は日立のオリジナル・マイコン(H8やSHマイコン)の拡販のための生販一体作戦である。
最初のオリジナル路線として開発したH8マイコンに関するモトローラとの特許問題は、1990年に全てクリアされた。世界市場で戦える製品系列が整備されたのを契機として、マイコン拡販のための大きなプロジェクトを起こそうという機運が設計開発部門、マーケティング部門、販売部門の間でかもし出されてきた。これを機会に、従来とは異なる方法で拡販プロモーションを行うべく、始まったプロジェクトがMGOであり、私が命名したものである。
従来の拡販活動では「xxx拡販プロジェクト」と呼ぶのが普通であったが、敢て「オペレーション」という言葉を使ったのは「こんどの拡販プロジェクトは今までとは違うのだ!」という決意を表すためであった。
実はこのプロジェクトのヒントになった事例がある。それは70年代後半にインテルで行われた「オペレーション・クラッシュ」つまり「粉砕作戦」である。私が87年に高崎工場長として赴任して間もなく、知人からウイリアム・ダビドフ著「ハイテクノロジー・マーケティング」が贈られてきた。この本では70年代後半にインテルとモトローラの間で繰り広げられた16ビット・マイコンの激しい市場争奪戦において、インテルが如何にして勝利したかについて具体的に記されていた。
当時、16ビット・マイコンとしてはインテルの8086が先行して市場導入され、圧倒的にリードしていた。ところが後発のモトローラが、性能的に優れた68000で大攻勢をかけてきたのである。インテルの販売部隊は恐慌をきたし、勝ち目がないと見て士気も低下していった。このような事態を打開すべく立ちあげたのが「オペレーション・クラッシュ」であり、その作戦を取り仕切ったのがウイリアム・ダビドフである。
ダビドフは「デバイス」と「プロダクト」の違いを鮮明に区別した。「デバイス」の競争は裸の製品の性能の比較である。即ち、処理速度、消費電力、メモリ容量など、チップのハードウエア特性である。その点では先行の8086は後発の68000にはかなわない。一方「プロダクト」は顧客が使うときの使いやすさまで含めた製品全体の良し悪しの競争となる。たとえばサポート・ドキュメント、レファランスボード、ソフトウエア、セミナー、 アベイラビリティなどの総合的な顧客サポートだ。
ダビドフは「デバイスで負けたとしても、プロダクトで勝つのだ!」という強い意志でオペレーション全体を指揮したのであった。これによってインテル陣営の指揮は徐々に回復し、競争は優位性を取り戻した。
そのような両者の熾烈な競争の勝敗を分けたのが80年のIBMでのデザイン・ウインであった。8086の姉妹製品の8088がIBM PCにD-inされたのである。これは新しいコンピュータの時代を拓く画期的な商品となって、その後インテルが世界トップの座を固めるのに大きな役割を果たした。
MGOのスタート
MGOがスタートしたのは91年2月である。その最大の狙いは設計開発部門と生産部門、営業部門、そして最終顧客とのコミュニケイション・ラインを直結することである。半導体の事業においては、技術も製品も市場も顧客も変化のスピードが極めて速い。従って一つの部門で起こった変化をなるべく早く、正確に他の部門に伝え、全体が情報を共有することが重要である。そのような任務をこなすためには高い技術的な水準が求められる。
設計部門を中心に優秀なマイコン技術者がこの大作戦のために動員された。
第1期(91年〜93年)は13名でスタートした。専任メンバーとなってリーダー役を果たしたのは阿部正義(支社担当)、川下智恵(国内担当)、堀田慎吉(海外担当)の3氏であり、当時の設計部門の主任技師である。また、技師クラスの専任メンバーとして活躍したのは越路誠一、竹島正彦、増田訓、山崎秀樹の各氏である。彼らはマイコンの技術や応用機器の真髄をしっかりと理解していた。即ち、文字通り「脂の乗り切った」若手の技術者達がこのオペレーションの先頭に立ったのだ。
MGOのスタートに当たって、前述の「ハイテクノロジー・マーケティング」をメンバー全員が読むことを薦めた。これを受けて英文の原書が人数分取り寄せられ、各人に配られた。MGOの活動を進めるにあたって、この本はバイブルのような役割を果たしたのである。特に、海外のマーケティングにおいては、本書から学ぶことが多かったことをメンバーの一人から聞いた。国内他社よりも海外で大きく伸びることができたのは、この本のおかげだと述懐している。
余談であるが、第1期の専任リーダーとなった川下氏は後日米国において、この本の著者のウイリアム・ダビドフ氏と面会の機会があった。サインをお願いしたところ、快く引き受けてくれた。この本は今でも宝物として大事に保管しているとの事である。
第2期(93年〜95年)は約30名。専任リーダーは佐藤恒夫(国内、支社担当)と菅原正彦(海外担当)の両氏である。さらにメンバーとして佐賀直哲、武田博の両主任技師と山浦忠、中田邦彦の両技師が加わった。
第3期(95年〜97年)は約80名と増強され、世界各地の顧客へのデザイン・ウイン活動が進められた。専任リーダーは芝崎信雄(支社担当)、川下智恵(国内担当)、菅原正彦(海外担当)の各氏である。また主任技師クラスとして荻田清、浦川澄夫、荒井保、岩下裕之、石井重雄、浅野道雄、藤永高正、松澤朝夫、邑楽隆之の各氏、技師クラスとしては武智賢治、土屋博一、田中欣也、山本克己、高松和也、三ツ石直幹の各氏が加わって、極めて強力な組織となったのである。
MGOのメンバーは勤務場所を販売部門の場所に移し、営業の海保副本部長が販売部門を取りまとめて、文字通り「生販一体」のプロジェクト体制となったのである。
プロジェクトの進捗状況は定例のF会議(本部長、副工場長以上の会議)において、技術本部長の安田元氏から報告がなされた。そのための資料作成などには、パソコン(アップルのMac)が使われ、当時としては先端的な手法であったが、1枚のコピーを作るのに30分を要するほどのスピードであった。
推進対象の製品は第1期ではH8マイコンが中心だ。これは日立のオリジナル・マイコンとして最初の重点製品であり、モトローラとの特許係争の終結を受け、晴れて拡販に打って出たものである。VTRやTV、オーディオなどの民生分野、コピー機、プリンタ、ファックス、パソコンなどの事務機分野、さらにはカメラなど幅広い市場への拡販が進んだ。
第2期以降ではSHマイコンが加わった。性能の面では世界的にも最高レベルの製品であり、特に「MIPS/W(ミップス・パー・ワット)」の数値は群を抜いており、最大のセールス・ポイントになったのだ。SHマイコンは、世界初のデジタル・カメラ(カシオ)、セガのゲーム機、ローランドの電子楽器、ヤマハの電子ピアノ、ザナビーやアイシンAWのカーナビなどに採用され、「デジタル・コンシューマ」と称する新しい応用分野を拓いたのである。
また、93年にはH8マイコンのF-ZTAT版(フラッシュメモリ搭載版)も市場導入され、世界最初の「フィールド・プログラマブル・マイコン」としてデザイン・ウイン活動が幅広く進められた。F-ZTATの強みはどんな少量生産の機器にも対応できることであり、システム設計者にとってマイコンを極めて身近なものにしたのである。その象徴的な事例がマイコン・カーラリーであるが、この点については第11章で述べたところである。
そして第3期になると、マイクロソフトの民生分野向け新OSのWindows CEがSHマイコンに搭載され、SHマイコンは世界の標準品の一角を占めるようになる。このインパクトは極めて大きなものがあり、項を改めて述べることにしたい。
さて、この「大作戦」は私が自分から言いだしたプロジェクトでもあるため、営業部門やMGOメンバーから要求があれば、極力時間の工面をして顧客の方に直接出向き、トップセールスの形で活動の支援をした。いうまでもないことであるが、トップセールスが効を奏するには販売部隊(特約店、営業部門、マーケティング部門、MGOメンバーなど)の日ごろの地道な営業活動がベースとなる。私の役割は顧客に対して「日立半導体のトップとして、マイコンに深くコミットしている」ことを明確に伝えるとともに、製品や市場の将来動向について「自分の言葉で」そのビジョンを語ることである。これは極めて大事なことであり、それによって、顧客サイドにおいては製品に対する信頼感と安心感が得られるのだと思う。
実は、マイコンなどアーキテクチャが絡んでいる製品の場合には「トップのコミットが極めて重要である」ということはウイリアム・ダビドフの「ハイテクノロジー・マーケティング」の中でもはっきり記されている。おそらくこれはインテル創業者のロバート・ノイスのことを指しているのだと思う。同氏が顧客訪問をしたときにどのような話をするかについては、いろいろと仄聞するところがあった。多くの顧客は彼の話を聞いた後で「ノイス信者」のようになるとのことである。ノイス氏は技術的にもICの発明など優れた業績を残しているが、販売の面においても「世界トップの半導体セールスマン」であったといえるのではないかと思う。
マイコンが日立半導体の大黒柱へ
さて、MGOが始まって1年余が過ぎた92年に、大きなマイルストーンがやってきた。拡販アイテムの最重点であったH8マイコンが、この年の6月に月産100万個を越え、売上は10億円を突破したのだ。関係者にとっては大きな喜びであり、拡販の勢いに弾みがついたのである。これを記念しての決起大会には、研究所、事業部、工場、営業各部門からの参加があり、大いに盛り上がった。図1の写真はそのときのスナップである。なお、その翌年の93年9月生産では売上倍増となり、H8は月産200万個を突破した。このように急伸したのはMGOの活動が極めて活発であったことの証左でもある。

図1 H8マイコンの100万個(10億円)達成の決起大会(1992年6月)
(左から金原和夫氏、牧本、木原利昌氏)
さて、ここでMGOの活動によってマイコンの売上がどのように伸びていったかを見てみよう。MGO開始前、91年のマイコン売上は月額45億円であり、大半がモトローラ系の旧製品(68系や63系)が占めていた。新製品(H8系など)は5億円であり、全体の11%に過ぎなかった。MGO活動を通じて新製品は倍々ゲームで伸びて行き、92年には10億円(同20%)、93年には20億円(同36%)、94年にはマイコン全体の売上が80億円であったが、新製品売上は45億円に達し、全体の56%を占めるに到ったのである。この時点でついに、新製品のH8マイコンとSH
マイコンが旧製品を凌いで主流の地位についたのであった。
MGOの第1期から第3期が行なわれた期間(91年〜97年)は日立半導体の激動期に当たっている。95年までメモリが大躍進して業績を牽引したが、96年以降は大不況に陥ってその勢いは失われた。メモリに変わって、マイコンが半導体の新しい大黒柱となり劇的な主役交代が行なわれた時期である。
この当時の組織は「プロダクト本部制」となっており、売上などの業績管理は(マ本)=マイコン・ASIC本部、(メ本)=メモリ本部、(汎本)=汎用半導体本部に分かれていた。95年前後の(メ本)と(マ本)の月次売上高の推移を見てみよう。
93/下は(メ本)189億円に対し(マ本)78億円で半分にも及んでいない。95/下になると(メ本)は大きく伸びて(年率42%)383億円となり、(マ本)も125億円と年率27%で伸びたが、(メ本)の1/3以下となっている。
しかし、この直後に強烈な半導体不況が訪れ、特にメモリは壊滅的な打撃を受ける。97/下では(メ本)107億円まで落ち込んだのに対し、(マ本)131億円となって、初めての主役交代となった。マイコンは文字通り、日立半導体の大黒柱になったのである。
このような目覚しい成果を支えるのに大きな力になったのがMGO活動であり、その名は次第に国内の同業他社の間で広がっていった。あるとき、MGOメンバーとの酒宴の席で聞いたことであるが、国内のライバル会社がMGOについて次のような噂をしているとのことである。
「日立の半導体で怖いのはSHマイコンだ。それよりも怖いのはMGOだ。さらにもっと怖いのは牧本さんのトップセールスだ」
これには多分にお世辞も入っているのであろうが、私が日立半導体のトップとしてH8マイコンやSHマイコン、F-ZTATマイコンに明確にコミットしたことが顧客に安心感を与えたことも、また確かであろう。
しかし、いうまでもなくMGOの名を高からしめたのは、この活動に情熱的に且つ献身的に取り組んだ若いマイコン技術者や営業マン達である。まことにアッパレ!というべきであろう。(2011年9月30日)